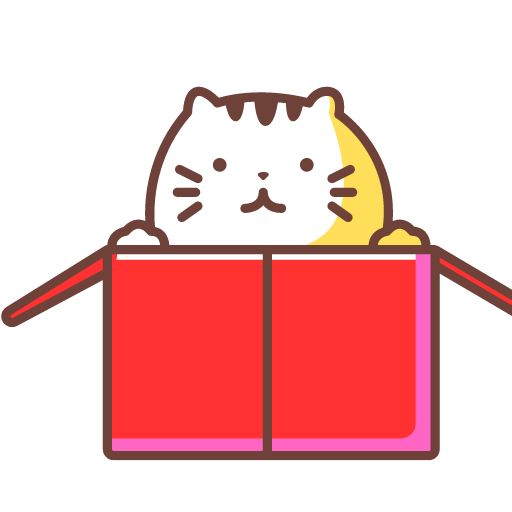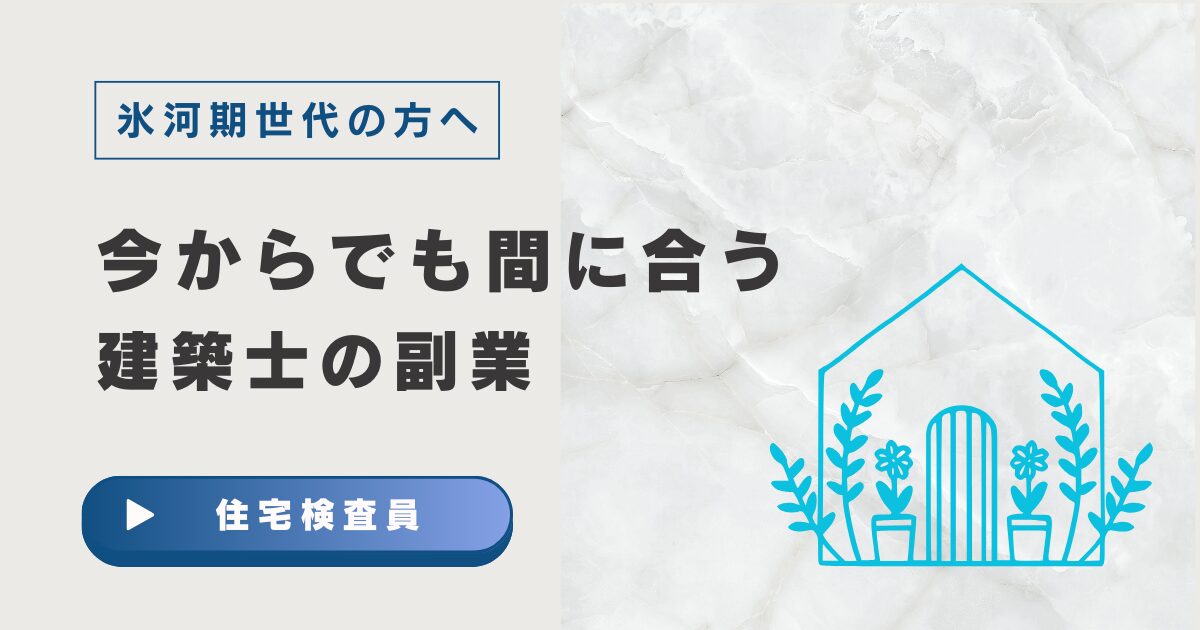「資格があるからすぐ始められると思ってた」ーー
私もそう思っていました。
でも実際に住宅検査員の事前研修に進んでみると、想像以上に準備が必要で、地味にお金もかかる…。
今回は、副業として住宅検査員を始めた筆者が、机上研修で直面したリアルな困りごとと、その解決法を本音で紹介します。
研修資料、準備物、テスト対策など、これから挑戦する方に役立つポイントをまとめました。
▶前回の記事はこちら→【住宅の検査員】今からでも間に合う建築士の副業~オンライン説明会編~

事前研修の流れ
前回のオンライン説明会の後すぐに説明会担当者の方からメールが届きました。
内容はこんな感じです。
メールの内容は机上研修と検査マニュアルをおくるから1週間程度で見て覚えてくださいということでした。その後は確認テストを受けて、契約に進むというような流れのようです。
「資格さえあればOK」なんて簡単に考えていた私は、ここでやっと現実を知ることに……。
机上研修で起きた3つの困りごと
机上研修は主に検査員の心構えとか注意点などなでした。
写真の撮り方や専用アプリの使い方など、この仕事を引き受ける上での最低限の内容が書かれていました。検査時の服装の規定も書いてましたがワイシャツやネクタイなどと細かく書いてあったけど後に実際に現場研修に入って気づいたんですが、誰もワイシャツなんて着てなかったです。あくまでマニュアルとして書いてるけど常識の範囲できちっとした印象になればそれでいいのかなといったところでした。その他にも色々机上研修中に困ったことがおきたのでそれぞれまとめました。
印刷問題:主婦には地味に痛い出費
机上研修の中に必要図面をファイル留めをすることって書いてあったんですが、ここで疑問というか心配ごとが、私ただの主婦なので家に図面が印刷できるようなプリンターが家にないのです。
ですのでコンビニとかで印刷するしかないわけなんですが、これが地味に高くて出費が嵩むことになるとは机上研修の時は気づいていませんでした。
説明担当の方も印刷のことは言ってなかったのでこの印刷問題は今の段階でも解決していません。(解決したらお知らせしますね)プリンターは買ったら数万円はするし、コンビニに毎回行くのは金銭面・時間面で負担が大きくて本当に困ってます。
金銭面でいうと、たとえば私の場合、A4サイズで白黒印刷が1枚10円、カラーが1枚50円。合計40枚ほど印刷したところ、コンビニで800円以上の出費に…。
月に数回あると、1,000〜2,000円/月の負担になります。主婦にとってはじわじわ効く出費でした。
準備物の多さ:え、こんなに必要?
前回のオンライン研修編でふれた準備物ですが、オンライン説明会では簡単な説明だったのに、実際の資料には準備物がどっさり。
とこんなにいっぱいありました。ノートパソコンもあると便利ですってことでした。
上記の中で数百円で買えるのはマスキングテープくらいです。あとは数千円~数万円します。
建築士の現場経験があっても、検査員としての持ち物には独特のルールがありました。
安全管理や第三者性が求められる立場だからこそ、事前準備の重要性を改めて実感しました。
でもさすがに最初からそんなにお金はかけれません。
説明書には書かれていなかったけど、ヘルメットや作業着なんかも準備しないといけないし、上記荷物を持ち運びする鞄も必要。いったいどんだけお金がかかるやら、、
思わず「ほんとにやるの?」と心が折れかけました。
せっかく自分の条件に当てはまる仕事だし、やっぱやーめたという前にとりあえず採用担当の方に相談したら、
「現場研修のあと、必要なものから少しずつ揃えれば大丈夫ですよ」ってことで話は落ち着きました。
実は上に書かれているもの全てが必要ではなかったことにも現場研修に行って気づいたんですが、それはまた現場研修編で詳しく書きます。
画像サイズ問題:スマホと両立が大変
検査用アプリでは画像が重くなりすぎるとうまくいかないそうで、サイズを640×480以上で最小のサイズにしてください」との指示。
言いたいことは分かるんですが、自分のスマホはプライベートでも使ってるし、わざわざアカウント分けて管理するのも面倒、画像サイズを変えるのも面倒。どうしようか考えたんですが、結局答えが出ず。
その後現場研修担当の方に実際どうしてるのか相談して解決することにしました。
詳しくは現場研修編でも触れますがフリーソフトをいれて簡単に解決することができました。(この時にノートパソコンがとても役にたちました)
施工管理とは違い、住宅検査では「画像記録」が最も重視されます。
専門職だからこそ、伝える・残すスキルも求められると感じました。

検査マニュアルと動画研修の実態
送られてきたマニュアル動画は全部で11本。
1本あたり30分〜40分あるものも…。
建築士として業務に携わってきた経験から見ても、検査マニュアルの内容は「現場対応力」と「記録の正確さ」が問われる設計です。図面の見方や建物の構造に関する基礎知識があると、理解が早く進みます。
検査マニュアルはYouTubeで見る形。映像で見ながら確認できるので比較的分かりやすくて良かったです。ただ、11個も動画があったので根気のいる作業でした。1つが30分以上の動画もあったので途中で眠くなりました。
私は2日に分けて見たけど、時間に余裕のある方、またはそんなに集中力続かないよーって方はちょっとずつ見るほうが頭にも残るかもしれません。
この検査マニュアルじたいは難しいことはないのですが、この後確認テストが待ってるので真剣です。結構長い動画を11個も見るのでいったいどこから出題されるかも、どんな形式のテストなのかも分からないので必死です。
「若い頃ならもっとスッと頭に入ったかも…」と、ちょっと落ち込みました(笑)
まとめ:孤独な個人事業、でも一歩ずつ進めば大丈夫
今回の研修で一番感じたのは、個人事業主って相談する人が身近にいなくて孤独だなということ。
会社だとちょっとしたことでも相談できたり失敗も笑いあえたりできるものですが、一人って思った以上に孤独です。仲間って大事なんだなって思います。
でも、ちゃんと聞けば答えてくれる人もいるし、同じように頑張ってる人もきっとどこかにいます。
一歩ずつ進めば、必ず前に進めます。
次回はいよいよ確認テスト編!
どんな問題が出たのか?落ちたらどうなるのか?赤裸々にお伝えします。