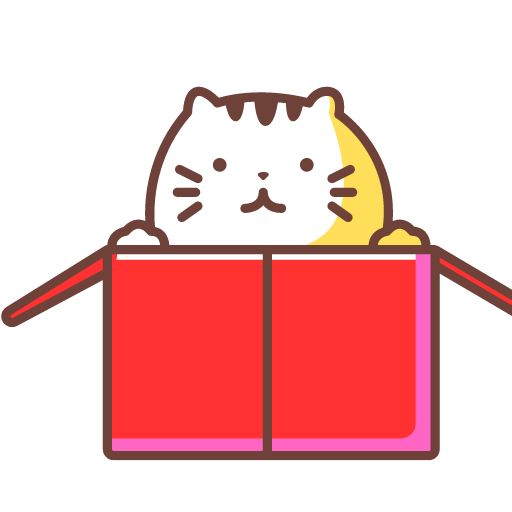「初めての定期講習、なんだか不安…」というあなたへ
このページにたどり着いたということは、建築士として初めて「定期講習」を受ける予定で、ちょっと不安を感じている方かもしれません。
実は私も、初受講したときに周りに経験者がいなくて不安だらけでした。

「終了考査って簡単って聞いてたのに、思ったより難しかった…」
「申込や当日の流れ、もっと事前に知っておきたかった…」
そんな体験から、「これから受講する誰かの役に立てば」と思い、このガイドを書いています。
(※筆者は総合資格学院で受講しました)
他ではあまり触れられていないリアルな情報や、終了考査の分析なども紹介していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
>>>2023年受講、管理建築士の受講の注意事項はこちらから
定期講習を受けられる主な機関
建築士の定期講習は以下のような機関で受講できます。
たくさんありすぎて迷ってしまいますが、料金や扱ってる登録講習区分(1級や2級、構造設計などの区分のこと)がそれぞれ違うのでご自身の予定・地域に合ったところを選びましょう。
主要な各講習機関の「ざっくり比較表」
| 講習機関名 | 受講方法 | 開催エリア | 土日開催 |
| 総合資格学院 | 対面/オンライン | 全国主要都市 | △(都市部中心, オンライン) |
| 日建学院 | 対面/オンライン | 全国主要都市 | △(一部あり) |
| 建築技術教育普及センター | 対面/オンライン | 全国 | ×(平日中心) |
| ビューローベリタスジャパン | 対面/オンライン | 都市部中心 | × |
※情報は執筆時点の目安。最新は公式サイトをご確認ください。
働きながらでも受講できる?日程はどう選べばいい?
定期講習は基本的に「平日1日」のみで完結するため、多くの方が仕事の合間を縫って有休を使って受講しています。
働きながらでも十分に対応できるスケジュール設計が可能なので、心配しすぎる必要はありません。特に、余裕のある日を選んだり、講習会場の場所をあらかじめ調べておくことで、当日もスムーズに行動できます。
忙しい方ほど、少しだけ準備しておくことで負担なく受講できますよ。
あえて金曜日に受けて、終了後いつもとは違うちょっと早い時間から飲みに行ってリフレッシュするのも楽しいですよ。(笑)
日程の選び方ポイント
- 講習機関によっては「土曜開催」もある
→ 特に総合資格学院や日建学院などの大手では、土曜日に講習を設定していることがあります(地域による)。
→ 希望する場合は、公式サイトで「○月 建築士 定期講習 ○○(地名)」などで検索を。 - 年度末・繁忙期は避けるのが無難
→ 建築業界の繁忙期(年度末など)に講習を入れると、仕事とバッティングする可能性が高くなります。余裕のある時期を選びましょう。 - 先の予定まで一覧できる講習機関を選ぶ
→ 総合資格学院や建築技術教育普及センターは、2〜3か月分の予定を公開しています。日程が選びやすいです。 - 小規模講習機関は開催日が限られているので注意
→ 地方や小規模団体が実施する講習は、年間数回しか開催されない場合も。早めに予約しないとすぐ埋まってしまいます。
終了考査についてのリアルな話
定期講習の最後には「終了考査(テスト)」が行われます。これは講習の理解度を確認するもので、1級建築士は全40問、2級建築士は35問が出題され、試験時間はどちらも60分です。試験といっても記述式ではなく、すべて四肢択一のマークシート方式なので、事前に過去問に目を通しておけば過度に心配する必要はありません。問題は講義の内容に沿って出題されるため、しっかり受講していれば十分対応可能です。またテキストを見ながらになるので大事なところに印をつけるなどしておくと良いです。
「建築士定期講習 終了考査 公表」で過去問検索!
対策としておすすめなのが、総合資格などの講習開催機関がが公表している「過去問を解く」です。
Googleなどで「建築士定期講習 終了考査 公表」と検索すると、公開されていることが多いです。
私の場合、周りから簡単だから大丈夫と言われて何の対策もとらずにいったら、思った以上にできなくて合格の結果がくるまではどうせ駄目だろうと本気で落ち込んでいました。その経験からも初めての方は過去問を解くことで当日落ち着いて終了考査にのぞむことが出来るので本当にオススメです。
私のちょっとした攻略分析
- 7~30問目までは、テキストの前から順番に見ていくと答えが見つかります。
- 1~6問目、2級の人だけがうける31問~35問目、1級の人だけが受ける36問~40問目は、テキストを前後に飛んで探すことになり、時間ロスしやすいです。
このことを知らなかった私は初めての試験で「どこに答え載ってるのー」とプチパニック状態に。この傾向を知っているだけでも、焦らず対応できるはずです。前述の過去問対策をすることで感覚は掴めると思うので実践してみてください。
ただし、これはあくまで私が何回か受けてみての分析なので参考にしてもらって自分なりの攻略方法をみつけてみてくださいね。
よくある不安Q&A(実際に後輩からの質問)
- Q終了考査に落ちたら免許剥奪されますか?
- A
そんなことはありません!
もし基準点に満たなかった場合でも、再受講するだけです。免許が取り消されることはありません。
ちなみに講習の修了率は99%以上。時間に遅れたり、途中で帰ったりしない限り、ほとんどの人が問題なく修了できます。
講習に落ちたことで免許剥奪になったら、多分建築士目指す人が減っちゃうと思います。皆さん多かれ少なかれ相当な努力をしてお金もある程度かけて、プレッシャーに打ち勝って建築士になられてると思うのでそんなことで剥奪されたんじゃたまったもんじゃないですよね。
- Q服装はどうすればいい?スーツじゃないとダメ?
- A
私服でOKです。スーツの人もいますが、90%以上は私服でした。
定期講習は「ビジネスイベント」ではないので、基本的に服装は自由です。
ただし、公共の場所で長時間受講することになるため「清潔感のある普段着」が無難です。
夏場は冷房が効いて寒い会場もあるので、軽く羽織れる上着があると安心です。
注意!遅刻・途中退室は厳禁
講義映像が見られなかった場合、その日は「未受講」と判断されてしまうこともあるそうです。
時間には本当に余裕を持って行きましょう。
まとめ:安心して受けるためのちょっとした工夫
初めての定期講習、緊張しますよね。
でも安心してください。高齢の方や、私のようにブランクのある方でも多く受講されています。
少しでも不安を減らすために…
- 会場や講習機関を早めに決めておく
- 過去問を1回でも解いてみる
- 当日は遅刻しないよう、時間に余裕を持って行動する
こうした準備で、心の余裕もかなり変わってきます。慣れてくると睡魔との戦いも待ってますが、またそれは先の話ですね。
応援しています!
最後まで読んでいただきありがとうございます。
私自身も不安だらけだったからこそ、「困った誰か」に届いてほしいと思っています。
この記事が役に立ったら、ぜひブックマークして他の建築系記事もチェックしてみてくださいね。
質問や追記の要望があれば、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。加筆していきます!