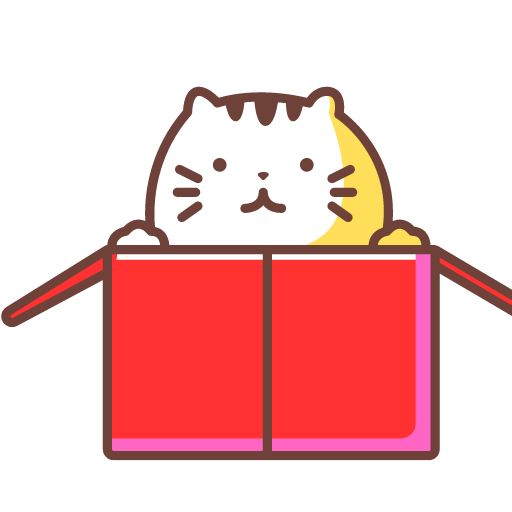つい先日、2025年の2級建築士・学科試験が終わりましたね。
受験されたみなさん、本当にお疲れさまでした!
今回この記事では、私が21歳のときに2級建築士の学科試験を受験し、一発合格(しかも99点!)したときの勉強法や実体験をお話しします。
受験前は「内容が広すぎて何から手をつければいいのか分からない…」と感じていました。
でも、3カ月間しっかり集中して取り組むことで、合格ラインを超えるのは決して不可能じゃないと気づいたんです。
これから2級建築士の試験を目指す方に向けて、どんな勉強をすれば合格できるのか、効率的な学習のコツは?資格学校ってどう?製図との両立は?といった疑問にもお答えしていきます。
この記事が、これから受験に挑むあなたの力になればうれしいです。

私のスペックと合格実績【3カ月で99点合格】
私は21歳のとき、工務店で正社員として働きながら2級建築士の学科試験を受けました。
この試験に向けて本格的に勉強を始めたのは、試験のちょうど3カ月前。
仕事と両立しながらの勉強は正直きつかったですが、日建学院のビデオ受講と自主学習を組み合わせて、毎日少しずつ積み上げていきました。
結果として、100点満点中99点という高得点で一発合格。今でも少し自慢です(笑)
🧠 得意だったのは法規。でも唯一落としたのも法規
得意科目は「法規」でした。これは仕事で関わっていたこともあって、感覚的に理解しやすかったからだと思います。
でも実は、唯一1点落としたのも法規。思い込みで回答してしまったので、ちょっと悔しい思い出です。
苦手だったのは「構造力学」。もともと計算があまり得意ではなく、最初は公式すら頭に入ってこなかったのですが、計算問題をパターン別に1つずつ潰していく方法が合っていたようで、徐々に慣れていきました。
🕒 勉強時間は「すきま時間×夜ファミレス」で確保
平日は仕事が終わってから4〜5時間。
朝は出勤前に1時間、昼休みにも30分ほど問題集を開いていました。
一人暮らしだったので、家事も最小限で、ご飯とお風呂以外はすべて勉強に使う生活。
どうしても集中できない夜は、近所のファミレスに行って深夜1時くらいまで勉強する日もありました。
👥 仲間の存在も支えに
嬉しかったのは、高校からの友達2人と一緒に挑戦し、全員が学科・製図ともに一発合格できたこと。
同じ目標に向かって励まし合える仲間の存在は、本当に大きかったです。
友人二人は日建学院の7カ月コースに通っていたので、受験する決断の遅かった私とはだいぶ差がありました。焦る気持ちが、机に向かう動機になったのも確かです。

合格までのスケジュール【3カ月でどれくらいやった?】
私が本格的に勉強を始めたのは、試験のちょうど3カ月前から。
それまでも仕事で図面や建築基準法には触れていたものの、資格のための「試験対策」としての勉強はほぼゼロでした。
📅 1カ月目(インプット中心):とにかく授業と過去問の選択肢を読む!
この時期は、日建学院のビデオ授業をひたすら受けることを優先。
平日は仕事終わりに週2回、休日は1回通学して授業を受けていました。
それ以外の時間は、過去問を解くというより、「読む」に近い勉強をしていました。
特に意識していたのは、五肢択一の選択肢を1文ずつバラして覚えるという方法。
正誤の理由まで理解することで、似たような問題にも応用がきくようになります。
📅 2カ月目(演習と暗記強化):ファミレスが第二の勉強部屋に
インプットが一巡したあとは、毎日4時間~5時間の演習と復習。
この時期は会社に行く前・昼休み・帰宅後のすきま時間を総動員して、1日5〜7時間は勉強していたと思います。
夜、家で集中できない日は近所のファミレスへ。
深夜1時まで勉強した日も珍しくありませんでした。
📅 3カ月目(仕上げ):解けない問題がなくなった!
試験3週間前には、「もう解けない問題はない」と言えるまでになっていました。
この時期は、過去10年分の過去問を3周以上まわし、「この肢は〇、これは✕」と瞬時に判断できる状態を目指していました。
構造や施工の計算問題も、「一気に覚えようとしない」「簡単なものから潰す」を徹底。
徐々に手ごたえを感じるようになり、不安よりも「いけるかも」という実感の方が強くなっていきました。
🧾 使用教材と勉強スタイルのまとめ
- 通学:日建学院(週2回)
- 自習:過去問集(五肢択一の選択肢を1文ずつ覚える)
- 勉強時間:1日5〜7時間(朝・昼・夜+休日は丸一日)
- 勉強場所:自宅/ファミレス
- 勉強スタイル:反復+アウトプット型(書いて覚える+解いて覚える)
この3カ月間は、正直「勉強以外してないな」と思うくらい集中していました。
でもそのおかげで、本番では構造以外の科目は時間が余るくらいスムーズに解けました。
構造だけは時間いっぱいまで粘って、計算問題を何度も見直し。
終わった瞬間、「やり切った!」という達成感があったのを今でも覚えています。

使ってよかった教材・勉強スタイル
勉強のベースになったのは、日建学院のビデオ講座と過去問題集でした。
ビデオ講座は、自分のペースで受けられる点が大きなメリット。
平日1回+休日1回の通学で、週に2回しっかり授業を受け、復習と演習は自宅やファミレスで行うというスタイルが、自分には合っていました。
🎥 日建学院の講座:ひたすら「聞く」ことで知識を定着
日建学院はビデオ講座形式なので、講師の話を「何度も聞ける」のが良かった点です。
内容が難しく感じた回は、家に帰ってテキストで復習。
また、講義のあとに自分でノートにまとめるよりも、過去問に結び付けて覚えていき、実際のテストでも使える知識に落とし込む、という流れを意識していました。
📚 過去問の使い方:肢をバラして「一文ずつ」覚える
2級建築士の学科試験は、五肢択一のマークシート形式です。
だからこそ、選択肢の「1文1文」をしっかり覚えることが非常に重要です。
私は過去問をただ解くのではなく、肢ごとに正誤をチェックし、その理由まで自分の言葉で説明できるようにしていました。
単なる「答え合わせ」ではなく、正誤の理由を覚える意識が得点力アップに直結したと感じています。
💡 五肢択一は消去法でもいける。だからこそ知識を「幅広く」
本番には過去問にない初見の問題も出題されましたが、選択肢のうち1つでも確信があれば、残りを消去法でカバーできるのがこの試験の特徴。
「全部覚えてないとダメ」と思い込むと苦しくなりますが、知識の幅を意識してコツコツ続ければ、確実に合格圏には届くと思います。
2級建築士の問題は、初見の問題数じたい多くないのでこの方法で十分に対応できます。
📝 苦手克服のコツ:構造力学は「1種類ずつ潰す」
私は計算問題が本当に苦手でした。特に構造力学は最初、公式すら覚えられずに焦っていました。
でもあるとき、

「一度に覚えようとしない。簡単なものから順に、一種類ずつ確実にクリアしていく」
という方針に切り替えてから、少しずつ前に進めるように。
たとえば「単純梁の曲げモーメント」「反力の求め方」「応力の基本式」などをテーマごとに区切って覚えるようにすると、心理的なハードルも下がりました。
☕ 夜の勉強場所はファミレス。集中できない夜の逃げ道
自宅でどうしても集中できないときは、近所のファミレスへ。
夜9時から深夜1時まで、ドリンクバー+ポテトで粘って勉強したことも何度もあります(笑)
周囲に人がいると、変に緊張感も生まれて意外と集中できるんですよね。
今思えば、このファミレスでの時間も、私の合格を支えてくれた大事な勉強場所でした。
今だから言える「これをやってよかった/いらなかった」
試験が終わってから振り返ると、「やってよかった!」と思えることもあれば、「正直これは必要なかったかも…」と感じることもありました。
これから受験を考えている方に向けて、実体験ベースで感じたことを正直にシェアします。
✅ やってよかったこと
▶︎ 過去問を「1文ずつ」覚える勉強法
五肢択一の問題を“肢単位”で理解・記憶していったことは、今振り返っても正解でした。
最初は時間がかかりますが、選択肢の引っかけパターンが見抜けるようになって、応用問題にも強くなれます。
▶︎ 朝・昼・夜の“すきま時間”活用
「フルタイムで働いてるから無理」と思っていたけど、朝・昼休み・夜と少しずつ時間を区切って取り組んだことで、毎日コンスタントに学習できたのが合格のカギだったと思います。
▶︎ 苦手科目をあえて最後まで逃げなかった
構造力学の計算問題に関しては、ギリギリまで苦手意識が抜けませんでした。
でも、1種類ずつ着実に理解していく方法を貫いたおかげで、本番では自信を持って解けた設問もありました。
▶︎ 仲間の存在が大きかった
高校からの友人2人と一緒に受験したことで、勉強の進み具合を報告し合ったり、落ち込みそうなときに励まし合えたのが、本当に心の支えでした。
「自分一人じゃない」って思えると、継続しやすいです。
❌ 正直、これはいらなかったかも…
▶︎ ノートまとめに時間をかけすぎない
最初は、講義後に丁寧にノートをまとめていた時期もありましたが、結局それを見返すことは少なくて…。
それよりも、過去問ベースで“使える知識”に直結させる勉強の方が圧倒的に効率的でした。
▶︎ 頑張りすぎ?なほど追い込んだかも(笑)
99点は嬉しいし誇れる結果でしたが、2級建築士は60点が合格ライン。
いま思えば、「そこまで追い込まなくても合格はできたかもしれない」とも思います。
ただ、のちに受けた1級建築士の学科では、同じように頑張っても受からなかったので、
「努力が確実に結果になる」のは2級までかも…という感想もあります。

正直、2級建築士の学科は難しい?
2級建築士の学科試験は、しっかり勉強すれば合格できる試験です。
実際に私自身も、3カ月の勉強期間で99点を取ることができました。
それでも周りを見渡すと、思うように点が伸びない人、何年も受け続けている人がいるのも事実です。
💡 難易度の正体は「広さ」と「継続力」
2級建築士の学科は、範囲がとにかく広いです。
計画・環境設備・法規・構造・施工の4科目それぞれに特徴があり、好きな分野だけを勉強しても合格できません。
とはいえ、一問一答のような知識問題が多いので、地道に繰り返せば、確実に点数は伸びていきます。
私の感覚としては、「覚える量は多いけど、出る内容はある程度決まっている」という印象でした。
⏱ 時間配分で焦らないために、過去問の習熟は必須!
本番では、構造を除けば全科目で時間に余裕がありました。
構造だけは計算問題があるため、最後の1分まで粘って見直していたほどギリギリでしたが、それ以外の科目はスムーズに解けたと思います。
これはやっぱり、過去問をしっかりやっていたからこその余裕だと思います。
「どこをどう聞かれるか」の感覚がつかめてくると、問題を読んだ瞬間に答えが浮かぶようになります。
✍️ 苦手科目があっても、戦略次第でカバーできる
私は構造が苦手でしたが、簡単な問題から順にクリアしていく方法で、徐々に得点源に変えることができました。
この試験は「全部解ける必要はない」し、「分からない問題を捨てても合格できる」のがポイント。
だからこそ、苦手をゼロにするより、“確実に取れる問題を落とさない”意識が重要だと思います。
⚠️ ただし、「なんとなくで受ける」人には厳しい
私の周りにも、「2級って簡単らしいから、適当にやってもいけるでしょ」と受けた人が何人かいました。
でもそういう人は、だいたい落ちていました。
特に製図まで含めて合格するには、ある程度の本気度と継続力が必要。
だからこそ、「今の自分の生活に合った勉強スタイルを見つけること」が、まず一歩目として大事なんだと思います。
製図試験は別物。学科と製図、意外と両立できた理由
2級建築士の試験は、学科だけでは終わりません。
多くの受験者がつまずくのが、その後に待ち受ける「製図試験」です。
私は学科に合格した年の秋、製図試験にも一発合格することができましたが、正直に言うと…仕事でまとまった時間が取れない中、いかに練習の枚数をこなせるか自分との闘いです。
📐 三角定規で受けた製図試験。ギリギリまで書き続けた本番
私には、平行定規を買うお金がありませんでした。
なので、製図の練習も本番も、すべて三角定規で対応。
正直ハンデは感じましたが、逆に「道具じゃなくて実力で勝負するしかない」という覚悟が持てました。本番では私以外にも数名三角定規の方がいましたがフリーハンドで受けた人がいるという伝説?もあるくらいなので、ちょっとだけ心が軽くなりました。
だけど試験当日は思った以上に緊張して、時間配分が狂い気味に。
終わってから「必須事項、書き忘れたかも…」と不安でいっぱいになり、発表までずっと落ち着きませんでした。
🧠 学科合格の勢いのまま、すぐに製図モードへシフト
日建学院では、学科の合格が発表されたその週末から製図講座がスタートしました。
気持ちの切り替えが早かったのも、同年合格につながった大きなポイントだったと思います。
最初はトレースの課題だけで精一杯。目標タイムの倍かかる状態でしたが、
週末には1枚仕上げる練習、平日は5日かけて1枚じっくり描く or エスキス練習、というペースで進めました。
📈 1か月半前には「余裕を持って描ける」状態に
時間はかかりましたが、描き続けるうちに「型」が身体に染みついてくる感覚がありました。
試験の1か月半前には、エスキスから製図まで、制限時間内に余裕を持って描けるようになっていました。
ファミレスではさすがに製図練習はできないので(笑)、この時期はずっと自宅にこもって図面を描き続ける日々。
振り返れば、学科以上に“生活を製図に合わせた”感じがありました。
👨🏫 製図の先生の存在が支えになった
日建学院の製図講師は、「図面の見せ方」「減点されない描き方」まで細かく教えてくれる先生でした。
自分では気づけないミスも毎回チェックしてくれて、「この先生に褒められたい」という気持ちがモチベーションにもなっていました。
また他の生徒の書いた図面も見ることができたのはとても良かったです。発想の違いや工夫の仕方など勉強になりました。
🔄 学科と製図、両立のポイントは「勢い」と「切り替え」
学科と製図は、内容も勉強法もまったく違います。
でも私が同年合格できたのは、学科でつけた集中力・習慣をそのまま製図に持ち込めたからだと思います。
勉強を一度止めてしまうと、再スタートに時間も気力もかかる。
だからこそ、「学科が終わったらすぐ製図!」のテンポで動けたのは、すごく良かったです。
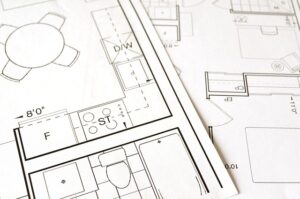
これから受ける人へ。私から伝えたいこと
私は21歳のときに、仕事と両立しながら、2級建築士の試験に挑戦しました。
最初は「絶対に受かる」とは思えず、不安の方が大きかったです。
でも3カ月、本気で勉強に向き合ったら、ちゃんと結果は出ました。
💬 2級建築士の試験は、頑張った人にちゃんと応えてくれる
この試験は「努力がちゃんと点数に返ってくる」タイプの国家資格です。
1級と違って奇問や複雑な設計課題はあまり出ません。
だからこそ、地道な積み重ねと、過去問の繰り返しが一番の近道になります。
🙌 同じ目標を持つ仲間がいれば、合格率はぐっと上がる
私の場合は、高校時代の友人2人と一緒に受験して、全員が同年合格できました。
悩んだときに相談できたり、「今週ここまでやったよ」と言い合えたりする仲間の存在は本当に大きかったです。
もし身近に同じ資格を目指す人がいない場合も、SNSや勉強会でつながれる時代。
1人で頑張らなくてもいいということを、ぜひ知っておいてほしいです。
🏗 資格を取ることで、仕事の選択肢が広がる
建築関係の仕事をしていくなら、2級建築士の資格は持っていて当然のスタートライン。
仕事の幅が広がるだけでなく、お客さんや上司からの信頼も変わってきます。
私自身、2級に合格してからは「一人前の建築士」として見てもらえるようになり、
仕事でも自信を持って提案できるようになりました。
✏️ 落ちても「向いてない」とは限らない。でも…
最後に、少しだけ厳しいことも書いておきます。
もし何年も連続で製図で不合格が続いているなら、それは「努力が足りない」ではなく、「もしかしたら適性の問題かも」と考えてみてもいいかもしれません。
向き・不向きは誰にでもあります。
だけど、一度本気でやりきってから判断することが大事だと思っています。
合格した先に見える景色も、きっと変わる
2級建築士の試験は、決して簡単ではないけれど、努力した人に応えてくれる試験です。
私自身、フルタイムで働きながら、三角定規片手に勉強漬けの半年間を過ごしました。
今思えば、「あのとき本気で頑張ったからこそ、今の私がある」と、胸を張って言えます。
この試験に挑戦する人は、年齢も立場もバラバラ。
でも共通して言えるのは、
💬「今の自分を、少しでも前に進めたい」と思っている人が、2級建築士を目指している
ということ。
試験の向こうには、「選べる仕事」「変わる自分」「変わる周囲の目」があります。
そして何より、建築士としての第一歩が始まります。
最後に、これだけは伝えたいこと。
「時間がない」「自信がない」…そんな気持ちを抱えていても大丈夫。
私も同じように不安でいっぱいでした。
でも、毎日の小さな努力が積み重なれば、ちゃんと届きます。
この記事が、これから2級建築士を目指すあなたの背中を、少しでも押せたなら嬉しいです。
🔗 あわせて読みたい
- 一級建築士講座といえば「総合資格学院」「日建学院」
1級建築士とありますが、2級建築士でも同じく参考になります👇👇