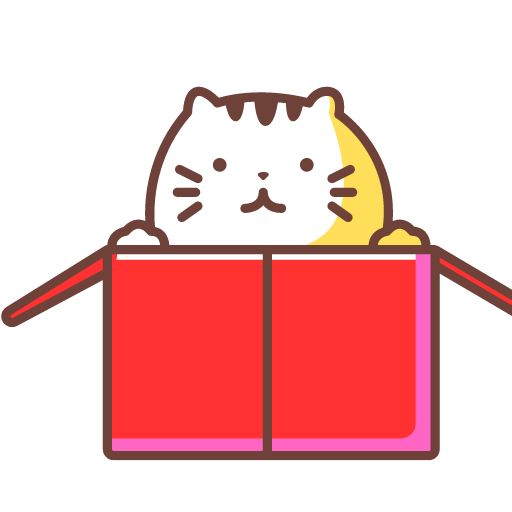これから建築士を目指す皆さんへ向けて、わたし自身の受験経験や、合格までに感じたこと・やってきたことをお届けしていきます。この20年ほど何度も挑戦しては落ち続けた人、途中で諦めた人、色々な人を見てきました。そんな私の経験があなたのお役にたてれば嬉しいです。
建築士を目指していたあの頃のわたしは、
「仕事・食事・睡眠以外、すべての時間を勉強に使っていた」といっても過言じゃありません。
そんな受験生活のリアルと、なぜそこまで本気になれたのか、そして働きながら合格した、試験への心構えについて学科と製図の二本立てでお話しします。
2回目の今回は学科試験・突破術編をお届けします。
私はフルタイムで働きながら、2度目の挑戦で合格しました。
仕事のあとに机に向かうのは正直きついし、「時間が足りない!」って何度も思いました。
でも、「時間がないなら、作るしかない」と開き直った瞬間から、少しずつ合格に近づいていったんです。
今回はそんなわたしの、実践的な学科突破術をお伝えします。
同じように働きながら勉強している方に、ヒントを届けられたら嬉しいです。
みけねこ26歳。
初めての1級建築士の試験へ挑戦。速報結果は合格ラインから2点足りたないことが判明。
当時、資格学校に通っていたが、もしかしたら今年の合格ラインにのってる可能性があるからということでそのまま製図の授業を受けることに。
製図の授業に何回か通ったところで、正式な不合格通知がきて、1回目の挑戦終了。
くやしすぎて、次の年頑張ろうと思う気持ちと、めちゃくちゃ頑張ったのに落ちた挫折感で建築の仕事を辞めようかと思い悩む日々を送る。
みけねこ27歳。
あと1回だけ受けてダメなら二度と受けない気持ちで2回目の挑戦。
結果は合格ライン+2点でなんとか学科を合格。
その後、製図試験へ。こちらは1発合格。
無事に27歳で建築士に登録!
毎日1時間半の“朝活”がすべてを変えた
当時は朝6時に起きて、6:15から勉強スタート。
出勤前の1時間半を「誰にも邪魔されないゴールデンタイム」にしていました。
眠いときは、まず昨日の復習から始めました。やってみると確かに昨日は覚えたはずのものが頭から出てこない。これめちゃめちゃ焦ります。焦りながらももう一度同じことをするのです。
その朝の焦りが仕事終わりの勉強のモチベーションに繋がります。
このままだと合格できないって自分で自分を追い込んでいました。やったつもりの勉強ほどこわいものはないです。
人間の脳が記憶を定着するまでに必要な回数は、一般的に5回以上とされています。しかし、記憶の定着には、学習内容、個人の特性、そして復習のタイミングも影響するため個人差があります。
復習のタイミングはとても重要なので是非覚えて実践してみてください。
私は下記の方法で記憶していきました。1級建築士は覚える量が膨大です。効率よく覚えるためにも、せっかく覚えたものが出ていかなようにするのがとても大切です。
通勤時間も有効利用!暗記系科目を重点的にこなす
通勤時間ももちろん勉強です。私は片道20分のバス通勤中はできなかった問題をひたすら繰り返す時間に使いました。通勤前の1時間半ではできなかったことをとにかくやりました。立ったまま片手でもできる工夫をしてましたが、今だと過去問アプリをやYouTubeも優良なものがとても多いので利用しない手はありません。移動の車の中や電車の中でプレッシャーにならず、達成感だけはちゃんと得られます。
法規や計画など、スキマ時間にぴったりの暗記系科目を重点的にするか、苦手な科目があれば移動時間はその科目だけひたすら頑張る等、ルールを決めると続けやすいです。
おすすめのアプリを紹介しているページがあるので気にある方はチェックしてください。
科目ごとの“得点目安”で戦略を立てる
合格基準点はおよそ、計画が11/20点、環境・設備が11/20、法規、構造が16/30点、施工13/25点、総合92/125点です。
全部を完璧にやろうとすると、時間も精神力も足りません。ただ極端に苦手なものがあってはダメです。私の場合、目標点を下げると実際はその下の点数をとってしまうことが多かったので基本的に満点を目指すつもりで全力でいきまいた。とはいえ現実的には難しいので自分の得意・不得意から受験1か月前のテストの目標点を以下のように決めました。
- 計画:目標16点(暗記で取れる)
- 環境・設備:目標16点(苦手でも最低限)
- 法規:目標25点(条文番号で整理)
- 構造:目標25点(計算の型を覚える)
- 施工:目標20点(実務とリンク)
これで総合102点です。1級建築士の本番では見たことも、聞いたこともない問題が必ずでてきます。そんな問題は捨てるしかないので、普段から目標は高くもっておくと、たとえ本番で捨て問に出会っても最後まで自信をもって挑むことができますよ。本番でうろたえたり、もう駄目だーってならないのも長時間の試験を受ける上でメンタル的にとても重要です。
モチベを保ったのは「1週間ごとの小テスト」
「とにかくやらなきゃ…」と漠然と机に向かっても、集中は続きませんでした。
そこで私は、休みの毎週土曜日に“自分だけの確認テスト”を作成していました。
月〜金の復習をまとめて挑戦するスタイルです。問題に何回も触れたほうがいいのは先ほども伝えたとおりです。何故土曜日にするかというと、日曜日にちゃんと勉強するためです。
実際確認テストをすると、意外と覚えていなかったことに気づきます。そうすると遊んでる場合じゃない!となるわけです(笑)
結果が見えると達成感があるし、1週間で何を覚えられて何が抜けたかが明確になります。
「ここまで来たから、来週もやろう」――その繰り返しが合格に繋がりました。
「できなかった日」は“記録するだけ”でもOKにした
私はどちらかというと完璧主義です。でもそれで精神的に潰れてしまったら元も子もないですよね。
やらない日、やれない日を上手に利用しました。
「今日は勉強できなかった」と落ち込むより、ただ「できなかった」とカレンダーに記録するんです。
たとえば、手帳に「×」をつけておくだけとかでもOK。
終ってみたら×はほとんどなかったんですが、とことん勉強していると本当にこれ以上やると逆に疲れすぎて効率が悪いなと気づくことがあります。そんな時は立ち止まって、休んで遊んでしまうほうが結果リフレッシュできてまた勉強への意欲がわいてきます。一人一人集中できる時間は違うと思うので自分なりのやらない日の見つけ方ができればベストかなと思います。
心の余裕が、長期戦にはいちばん大事だったと今では思います。
まとめ
- 朝の1時間半で合否が変わる
- 通勤時間もアプリや動画を活用
- 科目ごとの点数戦略で効率アップ
- 自作テストで1週間ごとの成果を可視化し出来ない問題をあぶりだす
- 「できなかった日」も大事な記録
これが、わたしの“働きながらでも合格できた学科突破術”です。
次回は「法規の条文整理、どう乗り越えた?」というテーマで、さらに深掘りしていきたいと思います!
「頑張ってるのに結果が出ない」と感じてる人や、「どこから手をつければいいか分からない」人に少しでもヒントや勇気を届けられたらうれしいです。